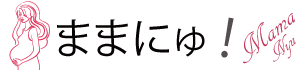予防接種が必要な理由
幼少期にたくさんのワクチンを受けるのは免疫力が弱く、感染症が出たらひどくなったり、あとで大変な病気になったりする可能性が高いからです。
免疫力の低い子供のうちに、ワクチンを打つことで病気のウイルスや細菌から守れます。また、予防接種は定期的に受けられて、お金はかからないので受けておいた方が安心ですね。大事なのは、子供を守るために親が積極的に行動することです。
予防接種を受けなかったらどうなる?
ワクチンは、絶対に安全だとは言えないし、副作用もあることがあります。
生まれたばかりの2、3か月の赤ちゃんに、いろんなワクチンを打つことに、親が反対することも少なくないようです。
ワクチンを受けなかったらどうなるのか、気になりますよね。
予防接種には、軽いものから重いものまで、いろいろな副反応が出る場合があります。
それに、アレルギー反応を起こすこと可能性も。でも、副反応の頻度は実際の病気にかかる確率よりは低いのです。
はしかなどの感染症は、ただの風邪と似たような症状が多いため、あまり気にならないこともあるかもしれません。
でも、ワクチンを受けるべきときに受けないと、ひどい状態になることもあります。それが取り返しのつかない事態につながることも。
実際に、ワクチンの副作用を心配して受けなかったせいで、病気になって大切な命が失われたケースもあります。
「あのとき、ワクチンを受けておけば…。」と後悔しても、もう命を戻すことはできません。
大切な命を守るために、親は責任をもってワクチンを受けさせてあげましょう。
予防接種はどこで受ける?
予防接種は「かかりつけの小児科」で受けましょう。
子供のふだんの様子を知っているかかりつけの小児科医で予防接種を受けるのがおすすめです。健康な子供でも、アレルギーや持病がある子供でも接種後の変化が出た場合は特にかかりつけの小児科の先生が頼りになります。
子供が生まれたら、近くの小児科を探してかかりつけ医を見つけましょう。1か月健診で予防接種の相談をしてみてください。かかりつけの小児科医は予防接種スケジュールなどを相談できます。BCGやコロナワクチンは、自治体の指定場所で接種することがありますので、自治体に確認しましょう。
予防接種の種類と受けるタイミング
ワクチンの種類と効果、受けるタイミングをまとめました。ここでは、ロタウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワクチン、四種混合ワクチン、BCG、水痘ワクチン、麻しん風しん混合(MR)、日本脳炎などの乳幼児期に打つ予防接種ワクチンの紹介をします。
※2~3歳になってから再度打つワクチンや、5歳以降に打つものもあります。今回は記載していませんが、接種漏れには気を付けましょう。
ロタウイルスワクチン
予防する病気:下痢や嘔吐で重症になることもあるロタウイルス感染症
接種時期:生後2か月からがベスト。14週6日までに1回目接種が必要
おすすめの受け方:生後2か月のヒブやB型肝炎ワクチンと同時接種がおすすめ
効果と安全性:ロタウイルス感染症の症状を軽減し、合併症を予防。
注意点:ウイルス種類により免疫が異なる。5歳までに何度かかかることもあります。
ヒブワクチン
予防する病気:細菌性髄膜炎や喉頭蓋炎
接種時期:生後2か月から3回接種、1歳すぐに4回目
おすすめの受け方:0歳で細菌性髄膜炎が多いため同時接種で早めに受けるのがおすすめ
効果と安全性:赤く腫れたりすることがありますが、予防効果が確認されている証拠です
注意点:生後6か月から病気リスク増加します。生後2か月から接種が大切。
小児用肺炎球菌ワクチン
予防する病気:細菌性髄膜炎や肺炎
接種時期:生後2か月から4回、1歳すぐに最後の接種
おすすめの受け方:0歳の病気リスクが高いためヒブワクチンと同時接種がおすすめ
効果と安全性:世界的に認められたワクチンで効果実証済み。
注意点:生後6か月以降の赤ちゃんにもリスクがあります。早めのスタートが重要です。
副反応:38度以上の熱や赤み、しこりが起こることも。
B型肝炎ワクチン
予防する病気:B型肝炎と肝臓がん予防
接種時期:母子感染予防は母親がキャリアなら妊娠中、それ以外は生後2か月から
接種回数:1回目はロタウイルスなどと同時接種、27日以降に2回目、4~5か月後に3回目接種
注意点:知らない間に感染してしまうことがある。遺伝子型Aにも注意
四種混合ワクチン
予防する病気:ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ
接種時期:生後2か月から1期は4回(1回目生後2か月、2、3回目3~8週間おき、4回目半年後)、2期は1回、任意接種あり
おすすめの受け方:1期は4週間ごとに他のワクチンと同時、2期は11歳で受ける(任意接種で百日せきの予防も)
副反応:腕の腫れや赤み、稀に全体の腫れがあります
BCG
予防する病気:結核
接種時期:生後5か月から7か月
タイミング:生後11か月まで、四種混合ワクチンのあとがベスト
注意点:スタンプ方式の接種後、乾くまで触ってはいけない
副反応:一時的な腫れやうみ、稀にリンパ節腫れも
水痘ワクチン
予防する病気:水痘(みずぼうそう)
接種時期:1歳から、2回接種が必要
おすすめの受け方:1歳でMRワクチンと同時、2回目は3~6か月後がおすすめ
注意点:1回の接種だけでは数年後に20~50%が発症。2回接種が推奨されています
効果と安全性:副反応少なく、2回接種で症状軽減
麻しん風しん混合(MR)
予防する病気:麻しん、風しん
接種時期:1期は1歳、2期は小学入学前
おすすめの受け方:1歳時、地域流行時は6か月から
副反応:5~20%くらいが発熱します。
日本脳炎
予防する病気:日本脳炎
接種時期:1期は生後6か月~、2期は9~12歳
おすすめの受け方:おたふく風邪ワクチンや水痘(みずぼうそう)ワクチンと同時接種も可能
大切:3歳からの接種が一般的。特例対象者もワクチンの受け忘れに注意。
予防接種のときに準備しておくもの
予防接種当日に必要なもの
- 母子手帳
- 予防接種予診票(記入済みの場合も)
- 健康保険証
- 乳児医療証
- 任意接種なら現金またはクレジットカード
予防接種予診票は早めに記入し、母子手帳とまとめて持って行くようにして忘れないようにしましょう。定期接種は無料ですが、任意接種のワクチンもある場合は支払い用の現金やクレジットカードを忘れないようにしてください。
その他の持ち物
- おむつ
- ミルク
- 子供の着替え
- お気に入りのおもちゃ
順番を待つ間にぐずるかもしれないので、おやつやおもちゃがあると便利。母乳の場合は授乳ケープも入れておきましょう。ただし、接種前後の飲食は避けて、副反応の判断をしやすくする必要があります。接種前に済ませておきましょう。
予防接種時の服装
暖かい時期であれば薄着にできますが、冬は重ね着してしまうと診察時に着脱が大変です。
服を脱がせるだけで子供の機嫌を損ねないように、上手な服装選びを心がけてください。
赤ちゃんの服装
予防接種では医師の問診や触診があります。着脱しやすい前開きの服を選びましょう。お座りができるなら上下が分かれた服、お座りができないなら股部分から着脱できるロンパースがおすすめ。注射する場所を出しやすい服を選んで、脱がせることも考えましょう。季節や会場の温度にも注意し、調節がしやすい服やブランケットを持っておくと役に立ちますよ。
大人の服装
大人は動きやすい服を選びましょう。子供の予防接種では、子供が動かないように膝の上で抱っこすることもあるためです。子供が暴れることもあるので、アクセサリーや時計は外して怪我を防ぎましょう。子供が緊張から吐いてしまったり漏らしてしまったりする可能性もあるので、大人用の着替えも持って行くと安心です。
予防接種後の過ごし方
予防接種後はすぐに帰ってゆっくりしたいところですが、すぐに帰宅はせずに大気が必要です。過ごし方についてまとめました。
接種後は病院で待機
ワクチン接種後は病院で15〜30分待機します。これは、まれに起こる「アナフィラキシー」という重大な副反応に備えるためです。副反応は基本的に接種後30分以内に現れることが多いため、接種後は病院内か近くで待機しましょう。授乳も30分以上は待ってからにしましょう。
帰宅後
予防接種後時間がたっても副反応が見えなければ家に戻り、できるだけ安静に過ごしましょう。赤ちゃんは疲れていることもあり、副反応が出ることもあります。元気なら普段通りの生活をしてかまいません。ただし、発熱や腫れがある場合は無理せず、お風呂はぬるめに、激しい運動は避けましょう。
翌日の過ごし方
副反応の発熱の場合、24時間以内に下がることがほとんど。通常の生活に戻れるなら、すぐに解熱剤を使わずに様子を見ましょう。副反応は翌日も続くことがあるため、長時間の外出は控えると安心です。
予防接種を受けられなかった・受け忘れてしまったら
定期接種は国が定めた予防ワクチンの決まった時期に受けなくてはいけません。期間内に受けないと、任意接種扱いとなり費用がかかります。定期接種は国が重要とする病気への予防方法で、個人の健康だけでなく社会全体の感染防止にも貢献するため受け漏れのないように気を付けましょう。行政や県から案内があるかもしれませんが、自分でスケジューリングして期限を確認しておくことも大切です。
体調不良などで予定通りに受けられなかった場合でも、指定年齢を過ぎたあとに受けることは可能です。遅れて受けても効果に違いはありませんが、定期接種の指定期間を過ぎると自費になります。複数の接種を受けそこなった場合は、どの予防接種を優先すべきか、他の接種との間隔についてなど、医師と相談して受けるようにしましょう。
接種した記録ができるアプリや母子手帳にも記入していけば忘れにくくなります。接種したタイミングで次の予約もしておきましょう。リマインダー機能を利用して、接種予定日の数日前にアラームが鳴るようにしておくのがおすすめです。