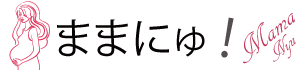更年期障害の特徴
更年期障害は主に50代前後に症状としてでやすいという特徴があります。
人によって症状の長さは異なりますが、閉経の前後5年から10年という期間更年期障害が発症しやすいという特徴があります。
更年期障害が発症してしまうのは、閉経の始まりが一番の要因です。
閉経前までは一定期間で生理がきます。
生理では排卵前から妊娠しやすくするエストロゲンというホルモンと、妊娠を継続させようとするプロゲステロンという二つのホルモンが正常に働いています。
しかし年齢と共に卵巣機能が低下してくると、排卵がおこらなくなり女性ホルモンのバランスが乱れてきてしまいます。
ホルモンバランスの乱れから、顔のほてり、イライラ、急な発汗、精神的な不安などの日常生活に支障が生まれてしまいます。
このような症状を抑えるためにはホルモン療法が一番効果的といわれています。
個人個人の体質によって適した治療法を見つけることが大事です。
漢方がもたらす効果
漢方は昔から長い歴史があり、多くの人に愛用されています。
病気の原因に対して効果的な薬を処方する西洋医学とは異なり、患者の症状や体質に合わせて漢方を調合していくのが特徴です。
西洋医学で処方される薬は一つのことに効果的をもたらすものが多いですが、漢方薬は一つの薬で様々な効果が期待できるのが特徴です。
そのため薬の種類をたくさん飲む必要がなくなります。
漢方薬は主に、気・血・水という3点が不調かどうか探りながら漢方は処方されます。
更年期障害の場合は、主に気と血に関する症状が多いのが特徴です。
頭痛は血流が滞ることでおき、お皿といわれていまします。
またほてりや動機は、気が乱れることによっておこるため気逆と呼ばれています。
漢方はこのように症状に応じて処方されることが多いですが、それと同時に体質によっても処方されるものが異なります。
漢方では抗体が強い人は実証と呼ばれ、虚弱体質な人は虚証と呼ばれ、どちらもなくバランスがいい人を中間証と呼ばれています。
この体質によって処方されるものが異なり、一つの薬で様々な効果が期待できます。
更年期障害と漢方薬
更年期は女性ホルモンの減少によってホルモンバランスが崩れることが原因で起きます。
そのため症状緩和の方法としてホルモン補充療法が推奨されています。
ホルモン補充療法に抵抗がある人、普段から服用している薬が多い人は、漢方を選択しています。
漢方は高いというイメージがありますが、中には保険適応内の漢方もあります。
そのため個人の負担額が少ないです。
また一つの薬で多くの効果が得られるため、薬の数や種類を減らすことにもつながります。