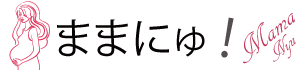食生活の変化
今芸能人や身の回りで乳がんになる人がとても増えています。
日本では年間4万人の人が乳がんになるといわれ、女性特有の癌として多くの人が認識しています。
乳がんは閉経後に発症しやすいですが、20代から40代の若い世代でも乳がんになる人が増えているのです。
そのためいつどのような形で乳がんを発症するのかわかりません。
しかし乳がんは早期発見することで5年生存率がとても高いため、定期検診がとても重要です。
乳がんになる要因の一つとして挙げられているのが食生活の変化です。
食事は私たちの体を形成されるもととなります。
日本では和食が日本食として昔から好んで食べてきました。
しかし最近では食の欧米化が進み、高たんぱく、高脂質の食事が増えてきました。
特に肉や魚などに多い動物性たんぱく質を好んで摂取する人も多いです。
これによって脂肪が蓄積されやすくなります。
そのほかにも野菜などもしっかり食べ、バランスがいい食生活を送ることができていれば問題ありませんが、どうしても現代人の食生活では野菜不足などが深刻な問題になっているのです。
このように不規則な食生活は脂肪に蓄えられるエストロゲンの量が過剰になってしまうという問題点があります。
乳がんとエストロゲン
乳がんの発症率が上がった要因として、女性ホルモンのエストロゲンが関係していることが分かっています。
食生活が豊かになり豊富な栄養素を幼いころから摂取することで、日本人の初潮が早くなってきている状態です。
それと同時に閉経の時期が遅くなってきていることから女性ホルモンが分泌している期間が長くなりました。
女性ホルモンの一部であるエストロゲンの分泌量も増えることになるため、乳がんの発症率が高くなっています。
女性ホルモンは女性の方が男性に比べて分泌量が多いです。
女性らしい体を作り上げるために必要なホルモンだからです。
しかし男性にも女性ホルモンがまったくないわけではありません。
そのため女性に比べると男性の場合は乳がんになる確率は低く、約1%未満といわれています。
女性特有の癌として、年代問わず注意が必要です。
ライフスタイルの変化
女性の社会進出が認められるようになり女性のキャリア志向が高くなってきています。
それに伴い恋愛よりも仕事を優先することから未婚女性が増えてきているのです。
また仕事を優先することで、婚期が遅くなり初産の年齢も年々高くなってきています。
これらの要因によって女性ホルモンが分泌される期間が長くなり、乳がんのリスクが高くなっています。
こちらのサイトの情報もオススメです。
>>健康サポート
女性にとって生理は女性ホルモンの分泌と大きな関係があります。
妊娠中や授乳中は一時的に排卵が行われなくなることで女性ホルモンの分泌量が低下します。
そのため乳がんの原因となるエストロゲンの分泌も少なくなってしまうのです。
しかし妊娠がおそいもしくは未婚の女性の場合、女性ホルモンの分泌量が多くなってしまいます。
このようなライフスタイルの変化が乳がんの発症率を挙げる要因として考えられています。